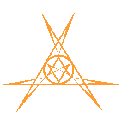
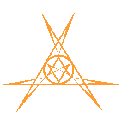
報道特集 御中
番組上の不適切な表現への異論無明庵 鈴木方斬
●●●◎◎◎○○○99年4月18日放映の『報道特集』で「自殺」について、 御社で取材とコメントをしておりましたが、 まずは、報道における用語の使い方についての訂正を要望します。 吉岡氏も、あるいは田丸アナウンサーも、 「自殺志願者」の心理状態を『病(やまい)』と発言しておりましたが、 医学上も、「自殺志願に関する思考が病と定義された事」はありません。 にもかかわらず、 『自殺志願者とは「心の病」を持つ者』という大変な誤解を視聴者に与えた この発言には、訂正を強く要求いたします。 まず、その明確な理由は、 いわゆる本当の精神病(脳外科的、あるいは心理的な病理)が原因となって、 自殺をする患者は存在し得ても、その逆はありません。すなわち、 自殺志願者イコール「精神病」という事は、事実としても成立しません。 これは単に、言葉尻を取って批判しているのではなく、 自殺の思考と病をイコールにする事が大変な誤りであり、不適切な表現で あり、この2つを混同して報道した事の責任を問うわけです。 自殺=精神的病気であるならば、世界中の文学者から科学者から宗教家まで、 無数の人達が病であったという事になってしまいます。それとも文豪の自殺 は暗黙のうちに許されて「凡人の自殺は悪だ」とでもおっしゃるつもりですか? なにはともあれ、死ぬまでにたった一度も自殺を考えた事もない人間のほうが、 遥かに異常であり、人間としての繊細な感性や知性を持っていない者だとすら 言えます。 また、実際に自殺するかしないか、は別問題としても、 自殺について、本当に思索し、なぜ自殺をするのか、について、あるいはその 是非について「周囲に迷惑と悲しみをもたらす」という、 そのような単純な白黒の付け方をしないで戴きたいものである。 というのも、死んだ故にではなく、逆に「生きている」が故に、 数百人、数千人、数万もの人間に迷惑や悲しみを与えてきた独裁者や 犯罪者や、政治家たちと、5人の人間に悲しみを与えた自殺者と、 一体、どちらが悪なのでしょうか?と私は問いたい。 また、もしも老いて、全く身寄りのない者が、独りで静かに自殺をしたと したら、その人は、一体「誰を悲しませた」と言うのでしょうか? それとも、その人の事を「心底悲しみ、声をあげて涙する社会やマスコミ」 というものが、この世のどこかにあるのでしょうか??? こうした問題を、よく考えもせずに、安易に自殺についての特集を組まない で戴きたい。青酸宅配事件が起きようが起きまいが、紀元前から、自殺は あったのですから。これは、社会性や報道や治安の領域の問題ではなく、 人類発生以来の問題なのですから。 インターネットのHPを書籍化した文献『自殺の自由化』を同封いたし ましたので、資料として熟読して下さい。 1999 4/18* * * * * * * * *学級崩壊についての私見
拝啓 筑紫哲也 殿無明庵禅道場 鈴木方斬
99年4/17、TBSテレビ放映の『 学級大崩壊 』を拝見しました。 そして、率直に、私見を述べさせて戴く事にしました。『社会崩壊を放っておくことの効能』について
学級崩壊の原因に、全くそっくりの「ある現象」をご存じだろうか? それは、最近警戒されている「耐性菌(多剤耐性菌)」である。 耐性菌というものは、言うまでもなく西洋医学の対症療法的な「処置」、 つまり、主に「抗生物質」がもたらした功罪である。 しかし、この『耐性菌』を現在の子供、あるいは大人、つまり「人間全体」 に当てはめてみれば、学校や家族の崩壊の原因が何であるか、 誰もが、少しは気がつかれるはずである。 その番組の中で、筑紫氏は『ほっておいたらどうか』とポツリと提案した。 それは「ある意味で」非常に正しいと私は観察している。 というのも、社会現象にしても、子供の変化にしても、出てくる問題に、 いちいち、我々は、あまりにも「いろいろな処置」をしすぎてはいない だろうか? 対症療法的な処置をする事のメリットは、当面の問題を素早く「抑制」 もしくは、「除去」出来ることだが、その結果が、現在の社会全体の ありさまなのである。つまり、抗生物質を使えば、目に見える症状は治まるが、 それと同時に「有用な素子までをも、同時に殺してしまう」。 いわば、教育現場も、政治経済も、含めて、現代社会の最大の特徴は 「抗生物質的療法社会」とも言えるだろう。 一方で、「放っておく」という事は、自発的な内側からの基準を本人が、 (誰のせいにする事もなく)作り出さねばならない状況を生み出す。 ここで、ひとつの極論を考えてみればよい。 「極論とは、哲学の最大の公式」だからだ。 たとえば、幼くして両親のいない孤児・・それこそ愛情にも恵まれず、 教育も受けられない子供がいたとする。この子供は場合によっては、 むろん、そのまま死んでしまうかもしれないし、生き延びるかもしれない。 しかし、全く放っておいたら、その子供はすぐに自らの「死活問題」に、 たった一人で直面しなければならないことになる。 そうなれば、そこから出てくる知恵は、社会的にどうであれ(つまり 善であれ悪であれ)本人にとっては、自分が自分で会得したものになる。 つまり、「放っておかれないと生まれないもの」が多くある。 完全に放っておかれるからこそ、誰が強要しなくとも、 「嫌でも自然に生まれてくるもの」が多くあるのである。 ・・・・・・・・・ さて、学校や社会で何か事があるたびに、 いつもで人間は「解決」と称しては、抗生物質を投与するかのように、 「その場かぎりの処置」ばかりをしてきた。 その結果、何をどうやっても解決や癒しの糸口すら見つからない、 家族や学校の「崩壊」は、見方によっては、 まるで「社会全体が耐性菌に犯された体」のようではないか? 何を投与しても、変態を繰り返して生き延びる細菌のようなのだ。 ・・・・・・・・・ そこで、ほんのちょっとだけ時代を溯って、物事を考えて戴きたい。 戦後の教育や家庭で一番最初に『問題』になった事はなんであったか? 誰もが「それ」をすっかり忘れているような気がするのだ。 戦後の家庭や学校を含めた教育現場で、一番最初に生じた病、一番最初 に口にされた教育問題は『過保護』だったのではないだろうか? つまり、『今の子供は過保護だ、過保護だ、温室育ちだ』と大人たちが 騒いだ「一時期」があったという事を、ちょっと思い出して欲しいのだ。 すべての発端は『過保護』から始まったように私には思える。 過保護の結果生まれる最大の弱点・・・それは『免疫力の低下』だ。 これは、身体のみならず、人間の「心」においても同じことだ。 ちょっと、鬱になったからといってセラピストにカウンセリングさせたり、 ちょっとばかり暴力をふるったからといって、PTAが問題にしたり、 校則を作ったり、逆に校則をゆるめたりと、 何でもかんでも、「ちょっと何かが起きるたび」に、マスコミが必要以上 に騒ぎ、学識者と称する者たちは、すぐに何かをそこに施してきた。 しかし、問題の多くは、実は、 「放っておけば、心の免疫力によって直ったはず」なのに、 そこに『余計な事』をしすぎた事、つまり過保護、過干渉であった事が、 現在の学校や社会の「崩壊の原因のひとつ」であると私は観察している。 過保護というのは、その発端は、おそらく戦前、戦時中に食べるものに 苦労した親が「自分の子供だけはそうなって欲しくない」との気持ちから 生まれたものなのかもしれない。 また、戦後アメリカの口にする「自由」を、日本人がどこかで取り違えて、 やみくもに「権利や人権」を必要以上に問題にした事も原因だろう。 ・・・・・・・・・ ここで、ひとつの例をあげるが、私が話で知る限りでは、昔の子供たちは、 場合によっては「今では完全なる虐待」とも言える行為を受けたり、 労働環境や、学習環境にあったのだ。 「でっち奉公」に出されたり「遊郭」に売られたりした子供もいるだろう。 また、子供ばかりでなく、青年たちも軍隊では、さんざんな暴力を奮われ ただろう。私の伯父などは、軍隊で殴られた後遺症で片方の耳がよく聞こ えなくなってしまった。 では、そうした暴力を受けたり、苦しい幼少期を過ごした彼らは、 その後、どうなっただろうか? 彼らは精神的なトラウマを背負ったり、犯罪者になったりしただろうか? ほとんどの人達は、そんな事にはなっていないのだ。 たとえば、今の子供が親から受ける家庭内暴力を、明治時代の子供が受け ても、心に傷など残らないだろう。仮に傷ついても、それは回復する。 ところが、もしも今の子供が、明治時代に平均的に親や教師から受けて いた暴力をうけたら、それだけで彼らは壊れて(キレて)しまうのだ。 私は何も「戦前の教育が良い」とも、「スパルタ教育が良い」、などと も言うつもりはない。しかし、学校や親、あるいは社会からの「過干渉 教育」と「過保護」は、スパルタ教育よりもさらに「最悪の結果」を招く という事が「大崩壊」の根源の一つなのである。 スパルタ教育には、大きなリスクもあるが、少なくとも、 ちょっとやそっとの事を他人から言われても、なんとも思わないだけの 「抵抗力」と「免疫力」を心につける効能だけある。 しかし、過保護は、子供の中に心の抵抗力を育てないどころか、 甘えと、都合のいい大人の方便の利用法と、差別なき平等という言葉だけ の主張を生み出し、結局は「精神的な免疫力の著しい低下」を生じた。 そして、少年犯罪が起きるたびに、心理学者や教育関係者がうおさおし、 しまいには、『賢治の学校』などという「集団セラピーワーク」までやっ ている。しかし、実は、これもまた、単なる『過干渉』であり、形を変え ただけの『抗生物質』や、良くてせいぜい『漢方薬』にすぎないのである。 親子の問題についてのカタルシス療法や、家庭問題の原因究明のための 記憶の逆行療法だのは、そんなものは既に15年以上も前から欧米で行われ てきた。しかしその結果、結局は人間は何一つも解決できなかったのだ。 ある「局部的な原因」、つまり「あー、子供の時のあれが原因だったのか」 などと、局部的な記憶と向き合って、それを吐き出すことは、 一時的には、心が軽くなるかもしれないが、結局「問題は繰り返される」。 なぜならば、それも当然で、 たとえ一つの心理的外傷の原因にいきついても、その原因には、 「さらなる、もっと過去の原因が連鎖している」からだ。 その良い例が、精神科の現場だ。 幼児体験の記憶の呼び出しによって直った患者は皆無だと言える。 なぜならば、ひとつの問題の原因である記憶や強迫観念をうまく吐き出 したとしても、またすぐに「次の強迫観念」を患ってしまうのが、 人間の常だからだ。 むろん、それらは最新の「脳内薬品」によって完治するわけでもない。 ・・・・・・・・・ こんな絶望的な人間社会の状況の中で、 実は、肉体の病でも、心の病でも、社会問題でも、教育問題でも、 そのすべてに有効な『マスターキー』というものが、 古代からこの星にも、そして宇宙のいたるところに存在している。 それは『放置』という処置法だ。それも、半端な放置ではなく、 『完全なる放置』である。 もしも、『忍耐をもって』、『完璧なまでに物事を放置する』と、 実は、ある一線を越えた時にそれまではカオスだった狂乱(つまり病) が、それ自体のエネルギーの持続力を失って消えてしまう事がよくある。 たとえば、(今の禅寺ではなく)本当の昔の日本や中国の禅寺では、 入門させても、弟子に全く何も教えない寺も多くあった。 何ひとつも教えないどころか、経典も一切読ませず、師は弟子に口も聞 いてくれない。ただ、とにかく毎日毎日、自分と向き合って座禅する事 だけが何年も何年も続く。 釈迦にも、こんな有名なエピソードがある。当時、彼の元に弟子入りす る者は、たったひとつ守らねばならない規則があった。 それは『まる1年間は、絶対に口をきいてはいけない』という規則だ。 一年後ならば、釈迦になんでも質問してもいい。 ただし、最初の1年は、弟子は完全な沈黙を命じられた。 入門してくる弟子は、それこそ、あちこちでいろんな経典や哲学を頭に つめこんで、釈迦と論戦でもしようと思って来た者もいれば、釈迦から、 仏法についてあれやこれや教えてもらえると思って来た者もいただろう。 ところが、釈迦の弟子がまずしなければならない事は、沈黙する事だった。 そしてその結果、1年後には、無数の疑問をかかえていたその弟子は、 その疑問の大半が自然に消失してしまったのである。 ・・・・・・・・・ ここから、我々が学ぶべきことがある。 教えない、助けない、対処しない。ただ、徹底して独りにしておく。 つまり、『放置の効能』である。 しかし、放置という事には、実は大変なハードルがある。 完全なる放置、つまり、良く言えば『あるがまま』というものは、 大変な「勇気」を必要とする。 なぜならば、動物を含めて我々生物の精神とは、 絶えず「生存しようする意志」で動いているからだ。 ところが、物事に対する「放置」という行為を成立するためには、 その「生存欲」を、いくばくか減衰させる必要があるのだ。 「生存欲」が我々の第一命令であるかぎりは、 人間は自分にふりかかる物事を、そのまま放置する事は出来ないからだ。 それでも、なおも、もしも我々が勇気と忍耐をもって、 完全なる「放置」つまり、自らの「生存欲を放棄した地点」に立ち、 そこで「起きている物事と共に死ぬぐらいの覚悟」で、 完全に無抵抗にしたら、一体、状況はどうなるだろうか? 実は、本当に打算なく、つまり心の曇りなく「完全なる放置」をした場合 には、多くの物事は、それ自体の道筋を見いだして終息するものなのだ。 一見すると、放置は「カオスと無秩序をもたらす」と人間は思ってしまう。 ひとつひとつの問題に対処し、早急に処置する事こそが人間的な行為、 または「人間の知恵」だ、などと思い込んでいる。 しかし、自然界の動植物たちや自然法則の、その見事な秩序の大半は、 「不必要に、物事に干渉しない事」によってこそ成り立っているという 事実を見るとよい。 ・・・・・・・・・ だから、最後にひとつの結論、あるいは提案をここに提示しておきたい。 これは非常に「哲学的な視点」の問題だが、 同時に極めて「実用的」な法則の応用でもある。 人間が、生きていて、最も『美しい瞬間』、いいかえれば『幸福な瞬間』 とは、実は、「生存」という目的を完全に忘れている時なのである。 人間たちは、生き抜こうとする意志が、人間の心のドラマを生み出したり、 その生きようとする葛藤から、科学や文化や愛や芸術が生まれた、と 「思い込んで」いる。 しかし、世の中には実は『全くの無心』から生まれた文化もあるのだ。 ただし、たとえば「自分の子供のために命を捨てられる母親」とか、 「自分の信じる誰かや、信じる思想の為に死ねる人間」がいたとしても、 それらはどこも美しいわけではないし、無心であるのでもない。 なぜならば、その場合には、自分は死んでも子供の「生存」を第一に考え ていたり、自分は死んでも、一方で自分が信じるものの「生存」や「存続」 には完全に執着をしているからだ。 つまり、「誰が生き残るか」「何が生き残るか」は問題ではないのだ。 そうではなく、問題の根は、 『過剰に生き残ろうとする意志そのもの』に歪みの根があるのである。 一方で、自分も他人もすべてを含めて、 「生き残ろうとも、生き残らせようともしていない者」がいたとする。 はたして彼は「人生を捨てた廃人」なのだろうか? 現代の人間の価値観によれば、彼は「無目的で、無気力な人間」と 見られてしまうかもしれない。しかし、 『生存』という「生物の最優先命令」が希薄になった人々の目の中に、 私は、この世に存在するすべての美しいものを多く見て来た。 「生存しなければならない」という基本的な恐怖から解放された者には、 独特の深い静けさがあり、安らぎがある。 たとえば、不治の病で末期に至った人間は、ある時期を境に、 この上もなく美しい目になる事がよくある。 ところが、人間は、いつでも「病と戦う力」ばかりをドラマにしたがる。 そして「病と共に死ぬ事の中に安心を見い出した人間」の美しさを受け 止めようとはしないのだ。 だから、『生存』、つまり 『生きること』『生きるための方法』『生きる目的』『生きる活力』 ・・・こんなものが、いつまでも我々の優先目的であるかぎりは、 人間は決して幸福にも安らかにもなりはしない。 その生きる力が、どんな科学や技術や社会を作り出したとしても、それは、 しょせんは緊張の生み出した作品、つまり死への「恐怖の産物」だ。 しかし、緊張や恐怖から生まれたものは、それを見る者、それに携わる者 にも、緊張と恐怖しか与えない。 幸福感の中から自然に生まれたものは、それを見る他人をも幸福にするが、 「不幸の克服のため」に生まれたものは、それを見る者も不幸にするのだ。 わが子に、親がどんなに多くの「偏愛」を注いでも、 その子が愛情深く育つわけではないのと同じ事だ。 ・・・・・・・・・無心の文化
一方で、人々が、完全に忘れてしまった、ある特種な文化、そして社会の 原理が、日本やアジアにはある。 もはや、現代では、それを理想とする事は出来ないが、 ひとつのサンプルとして、一度は、人々は思い出すと良いだろう。 その文化の最大の基盤は、「生存欲によっては成立していない事」だ。 むしろ、命などは、いつでも捨てる覚悟によって成立しているとえ言える。 それは、自分の命を削って他人の命を助けようともしていない。 むろん、他人の命を削って自分の命を助けようともしていない。 その文化は、現れては消え、消えては何度も地球に現れて来た。 その文化、その教育、その社会は、 過去にも、そしてこれからも、たったひとつの原則によって成立している。 その原則とは、愛でもなく、犠牲でもなく、戒律でもなく、道徳でもない。 その原則はただひとつ『無心』である。 その文化、その社会の原型は、中国では老子によってタオイズムと名付け られ、釈迦によってダルマと名付けられ、禅宗では「無」または「仏性」 と名付けられた。 それは「善良な市民」を生み出すのでもなく、 「柔順な子供」を育てるのでもなく、元気で丈夫で「社会の役に立つ子供」 を育てる事も、その社会の目的にはしていない。 その体系、その文化は、ただ、「無心な人間」を育てようとする。 なんの計算もない人間。 なんの目的もなく、ただ今の瞬間を生きて死ぬ人間。 なんの損得勘定もなく、ただ自由無碍に楽しみ、 時にはまるで阿呆のように、 死ぬとか生きるとかという緊張から解放された、 「静かで自然な人々」を生み出そうとしてきた。 学級崩壊、家庭崩壊、社会崩壊も、それを解決しようとするのではなく、 もしも、忍耐を持って、「とことん壊れるままに」できるならば、 それは、いずれ、それ自体の自発的な秩序を生み出すことになるだろう。 「破壊」もまた、それ以上の破壊はないという「限界」が必ずあるからだ。 ただし、生きる事、生きる手段、生きる意味ばかりに囚われている限り、 人間は、決して「放置」というこの万能薬を使いこなすことはできない。 「放置という万能薬」を使えないのならば、 『無心という、健康な精神』も得る事はできないだろう。 1999 4/17 18:55 鈴木方斬追伸
もしも、いつの日か、あなたのコラムである『多事争論』が最後の日を 迎えた時、その最後のテーマ、表題が、 『無心』の2文字になっていたとしたら、 それは、とてもパラドキシカルで、 意味深い最終回になるように思います。これから急増しそうな『介護殺人』
養護老人ホームの実態は、まだ断片的にしか報道はされてこない。 また、施設現場での「介護士と老人の間の虐待」、または「老人同士のいじめ」なども、 1999年3月現在では、まだ大きくは表面化はしていない。 言うまでもなく、多くの産業が政府と結託して、 利権がらみで介護ビジネスに目をつけている。 施設の建築をとりまく業者の利害関係、 施設に配備する医療器具の業者の利害関係、 そして、介護士養成学校の利害関係などが渦巻いているわけだ。 このまま国民の4分の1が老人となった時には、 介護ビジネスと葬儀社が国内の経済の重要な歯車の一つとなるのだろうか? しかし、これから頻繁に続発する可能性があるのが、介護士のストレスによる、 老人への虐待、もしくは殺人だ。 ・・・・・・・・・ 現時点では、幸いにも介護士はある程度の現場経験を積んだ者が中心であろう。 しかし、現在既に、介護士不足から、施設内で痴呆症の老人が問題を起こすたびに、 少ない介護士が、うおさおしている所もある。 また、何度同じ事を厳重に注意しても、問題行動を繰り返す老人も多い。 その結果、老人を怒鳴ったりしてしまう介護士も増え始めている。 むろん、これらは病から来るものであるから老人に責任の全部があるわけではない。 今後、こうした問題は、企業や行政がビジネスや、あるいは政治的思惑から世論の指示 を得ようして介護施設やその要員を養成し始めた時点から頻繁に起きるだろう。 というのも、介護士を「量産して養成」などしようとすれば、当然の事として、 実習も形だけを学んだだけになり、現場での経験もろくにない介護士が増え、 しかも、介護にはある程度の体力がいることからも、その介護士の年齢層は、 いわゆる「キレやすい世代」に集中してくる。 今でさえ問題を起こしている中学生や高校生が、仮にもう少しばかり年齢を重ね、 その時に、就職難や、需要の高さから介護士という領域に就職したとしても、 必ずそこでは、事件が発生するだろう。 むろん、その全員が問題を起こすわけではないが、確率的に考えても、 あとほんの数年で、こうした養護施設での虐待や殺人事件が急増する事は間違いない。 また私見では、介護は、おそらくビジネスとして成立しないと見ている。 老人たちの資産である年金や貯蓄といっても、それらは増加するものではない。 介護にかかる人件費や設備投資と天秤にかければ、決して黒字になるものではない。 そうなれば、さまざまな「手抜き介護」や、極端な場合には、契約金さえ前払いしたら、 あとは、「次が控えているので、早く死んでくれ」というような態度の施設も出て来る。 そして、老人ホームには常に、葬儀社や保険屋が出入りしているが、 特に、葬儀社の場合には、生前契約などを老人に勧めて、年金や貯蓄の一部を早めに 自分たちへの支払いに確保しようとする動きもあるだろう。 こうして、よってたかって老人たちの少ない貯蓄を見込んで利害関係が乱脈するが、 結局は、介護ビジネスは、経済的には数年であっと言う間に行き詰まると私は見ている。 また、医療現場や介護ビジネスの現場、そしてそこに出入りしている業者も、 それぐらいの事は、初めから計算ずくのはずだ。 つまり「老人が増えるから、これからは介護ビジネスが成立する」などと吹聴しては、 さっさと医療器具や介護ベッドを売り付けたり、施設の建設業者が儲けて、 そのあとは「さっさと手を引く」というわけだ。 ・・・・・・・・・ そして、当然の事として、老人たちの自殺や病死も増えるだろう。 この不況では、今後は施設にも入ることの出来ないホームレスの老人たちも、 どんどんと増えるからだ。では、本当は何が必要なのか??
人間が、残された老齢の時期をどう過ごすかという、それぞれの人生観が異なるために、 異論もあるだろうが、私の私見では、本当に必要なのは、 老人たちが、『安心して死を迎えられる施設』なのではないだろうか? 別にこれは自殺の施設を作れという事ではない。 しかし、治療や介護を、老人自身の意志で拒否が出来て、しかも、 静かに死を迎えられる施設が必要だという事だ。 私の祖母もそうだったが、老人は暗黙のうちに新薬の実験に使われる事もよくある。 また、必要もないような薬や、なんの役にも立たない薬、場合によっては、副作用で 病状が悪化するような薬まで、大量に老人に持たせて、病院は薬価差益で儲けるものだ。 しかし、人生とは、ただ元気で長生きすればいいというものではあるまい。 病気には「病気の中でこそ考えられる事」も多くある。 だから、老人に趣味や生きがいを持つ事を「無理強い」すべきでもない。 またボケを進行させないように、踊らせたり、歌わせたりすべきでもない。 「老人力」などという、実に馬鹿げた言葉を提唱する馬鹿者がいるが、 老人の本当の美しさとは、老人たちの人生経験や知恵ではなく、 その「無力な静けさ」にこそあるものだ。 ボケとは、介護士にとっては迷惑かもしれないが、 ボケてゆく老人にとっては、それはある種、自然なことであり、幸福な事でもあるのだ。 長い年月を、生きる緊張の中で過ごしてきた老人たちなのだから、 最後ぐらいは、「静かにボケてもいい」というものではないか?私の母の死
私の母は、いつも口癖のように、次の2つの事を言っていた。 ひとつは、「死ぬときには、ポックリと、一発で死にたい」 もうひとつは、「誰かに迷惑をかけてまで長生きなどしたくない」。 母は大病というものをした事はなかったが、足に外科的な病気があったために、 特に60歳を過ぎてからは、次第に歩くのが困難になってたいた。 70歳のころには、階段の上り下りが困難となり、買い物などは私が行っていた。 家の中では歩けていたので、家事には大きな問題はなかったが、それでも、 73歳のころには、夜中にトイレへ行くにも立って歩く事は出来なくなっていた。 歩くには歩けるのだが、足腰がある程度動くようになるまでに数分かかるのである。 足に病があると、とうぜん脊椎のゆがみから、腰が痛んだり、目に障害が出たりもする。 また、年を取れば、やはり小さな切り傷や、腫れ物でも治りがとても遅くなる。 そんなわけで、持病の足以外には内科的な病理はほとんどなく、 元来丈夫な人だったので、普通に元気に過ごしていた母だが、 死の1年ほど前からはさすがに、疲れが溜まる様子だった。 しかし、医者と薬が大嫌いな人だったので、市販の漢方薬一つ飲ませるにも、 私が説得するのは大変だった。 ・・・・・・・・・ 死の1年ほど前から、母の寝顔に、普通ではない静けさ、つまり死相が現れていたのを 覚えている。普通の寝顔ではない、非常に深い「静けさ」が母の寝顔に見え始めた。 それはかつて、祖母の葬儀の時に見た死に顔にそっくりだった。 だから、私もいずれ、いつか母が死を迎えるだろうと言うことは、覚悟をしていた。 ところで、その「寝顔」は、ある意味では最も本質的な意味での「瞑想的な顔」だった。 私が、祖母(母方の母)の「死に顔」を見た時の事は、今でも記憶している。 これほどまでに美しく静かな顔は、見たことがないという事が印象の全てだった。 生きている人間が、どれだけの座禅や瞑想をしても、このような静かな表情になる事は ない。しかし、この死の表情こそが本当の瞑想の極致であると当時の私は強く感じた。 その後、私がそのような顔を、死人の中にではなく「生きた人間」の中に見た事は、 たったの2度しかなかった。 ひとつ、それはインドの「和尚」の講話ビデオの、あるワンシーンの中に見たもの。 そして、もう一人はEO師が、時折見せた異常に静かな顔だった。 全く思考のかけら一つもよぎらないような、あれほど「死の静寂に近い表情」、いや、 「死の寂静がまさにそこにある」という生きた人間の顔は、それ以来見たことはない。 ・・・・・・・・・ さて、母の話だが、そんなふうに、母は、少しずつ、少しずつ弱っていった。 そして、ある朝、母は風呂場に倒れていた。 いつもなら私は寝ている時間なのに、なぜかその日に限っては、早めに起きたのだった。 風呂場の電気がついているのに、音がしないのを不審に思って急いで行ったところ、 母は倒れていた。出血や吐血はなく、また素人目には外傷もなかった。 まだ体が普通に暖かく、息もしていたので、私は急いで救急車を呼んだ。 そして、病院に運ばれ、意識を取り戻すことなく、その28時間後に母は他界した。 死因は、脳内出血と告げられた。特に高血圧という事もなかったはずなのだが、 何ぶんにも医者嫌いのため、30年以上も診断の記録がないのでいつから兆候があった のかは分からないが、おそらく、少しずつ病は進行していたのだろう。 しかし、疲れやすくなったという以外には、日常生活には、ほとんど支障はなかった。 意識不明の母の容体に対して、私が医師に真っ先に聞いた事は、 「倒れた時に、苦痛があったかどうか?」という事だった。 私が、人間の死に際して、最も懸念するのは、 生きるか死ぬかの問題ではなく「苦しみ」の有無であるからだ。 医師から聞いた限りでは、 小規模の脳内出血の場合には、頭痛が続いたり、吐き気を感じたり、 まだ少し動く体を引きずって、なんとか歩こうとしたりする事もあるが、 これほどの大量の突然の脳内血管の破裂による出血だと、 出血とほとんど同時に意識を失うから、苦痛はほとんどなかっただろうという事だった。 これは私の推測にすぎないが、 多くの脳内出血の経験者(この場合には助かった人)の言葉から考えると、たぶん、 ガツンと後頭部を強く殴られたような痛みを一瞬感じた直後に、母は意識を失ったよう である。 そういう点では、母が苦しまなかった事は、母にとっても、私にとっても何よりの救い だった。また、母は意識不明のままで他界したが、これもある意味で幸福な事だった。 人によっては、死の時に身内に何か言い残したことがあったり、誰かに会いたいと思う こともあるだろうし、死の瞬間をしっかりと意識して死にたい者もいるだろう。 しかし、母の場合は「他人様には絶対に迷惑をかけたくない」という思いが人一倍強い 人であったし、もしも意識があったら、かえって私や兄に対して、いろいろと余計な 心配をさせてしまったかもしれないと私は思う。基本的には、何ごとにも楽天的な母 だったが、さすがに死の間際では、人はいろんな事を考えてしまうものだ。 意識がなかった事は、私や兄、そして駆けつけた親類の人達と話すことが出来なかった という事では、悲しい事だったかもしれないが、母の几帳面な性格上を考慮すると、 むしろ非常に幸運な事だったと私は思っている。 日頃から、いつもいつも、「他人に迷惑をかけてまで生きたくない」 「死ぬときは、眠るように死にたい」と言っていた母は、まさに、その通りに、 死を迎えた。これはある意味で、非常に「幸福」な事だと私は思う。 なぜならば、人は、めったに「自分の死に方を選べるものではない」のだから。 ポックリ寺に100回お参りしたって、ポックリ死ねるわけではないのだから。 ・・・・・・・・・結語
老人たちが、静かに死ねる施設
無理やりに「長生き」させられて、「元気」でいさせられて、 「趣味」をもたされたり、そして、さんざんに手厚く介護されて、 薬で治療されて過ごす『介護生活』というものがある一方で、 私の母のように、ほんとうに「静かで、見事な散り方」をする死もある。 果たして、どちらが、幸福なのかは、人それぞれだが、「人それぞれ」であればこそ、 老人に、むやみやたらに、「生きる希望を焚き付ける」ような行為や、 老人たちを医療ビジネスや、介護ビジネスの対象にするような行為は止めて欲しい。 むろん、介護や治療を受けたい人は、好きに受ければいい。 しかし、治療や延命処置を拒否して、 「静かな死」を迎える事を選択する老人の為の道、 そして、その為の「静かな専用施設」もまた、 国が率先して作るべきであると私は考えている。 ・・・・・・・・・ ただし、「現実的な問題」で、困難になりそうな事は、 入院時の、本人や家族と施設側の「契約形式」をどうするかという事と、 施設の設備内容の問題である。 というのも、ある老人は、病気治療は一切拒否するが、下の世話はして欲しい、という 場合もあり、ある老人の場合は、途中までは治療を続けて欲しいが、末期的になったら 治療をやめて欲しいという場合もある。 また、特に病状がなくとも、次第に弱って自然に死に至りたいということもある。 こうした多種多様の症状や本人の希望に合わせて、本人が希望する治療や世話の限度を 一人一人個別に契約した場合には、 そうした設備の施設は果たして「病院」としての認可を受けられるのかが問題になる。 今後、もしも日本では、尊厳死や治療を受ける事を拒否出来るような施設の具体化が、 「医療機関」という名目では実現ができないのであれば、 最悪の場合、それは『治療や延命処置に関する自己決定権を、個人の信仰の問題とする』 ような、ある種の宗教法人の形で成立させ、 そうした自由な晩年を過ごすための施設を、その組織が作るしかないのかもしれない。 1999 3/12 鈴木方斬 ちなみに、私の母の遺骨は、簡潔な葬儀ののち、散骨をして自然の中へと帰した。 詳しくは『完全自然葬マニュアル』をご参照戴きたい。
この空間は 1997/08/15 に生まれました。